- その他
【対談記事】 コスト比較も、履歴管理も、AIが味方に。購買業務を次のステージへ。

近年、材料費を筆頭とする市況価格の高騰や、海外競合との競争激化が自動車業界の経営課題になる状況下、「量産図面出図前」にいかにコストを作り込むのか、という点が重要視されています。コストの8 割は設計段階で決まると言われるなかで、スピーディに最適コストを目指すことは調達起点での経営貢献において極めて重要なテーマです。一方で、コスト比較のための比較表作成業務や、比較対象となる類似部品の情報探し、分析データ準備などが大きな工数を占め、本来力を割くべき本質的な「コストの作り込み」業務をやりきれないという事態に陥っている企業も少なくありません。このような背景から、NAGASEは自社のCVC戦略の一環としてA1A株式会社との資本提携を行い、同社が提供する「UPCYCLE(アップサイクル)」というサービスを通じて、調達部門の効率化とコスト最適化をサポートしています。本対談では、A 1 Aの松原脩平C E Oにご登場いただき、U P CYC L Eの導入企業である河西工業株式会社の下原敬CPOとともに実務段階での課題と将来展望について探りました。
情報の属人化をなんとかしたい──UPCYCLEを始めたきっかけ
松原(A1A) 「UPCYCLE」開発の発端は、調達・購買業務における情報の属人化をどうにかしたいという思いからでした。
知識、スキル、そして情報──この3つは調達組織として最適なコストを目指す上で個人に依存しがちです。
すべてをITでシステム化すれば属人化が解消されるのかというとそうではなく、
最終的な判断やサプライヤー様との交渉は人が行う領域として存在します。
そこでまず一歩目として、「情報の属人化の解消」に目をつけ、
見積書などのバラバラなフォーマットをAIで統一・整備するプラットフォームを作ろうと考えました。

下原(河西工業) 河西工業では従来、サプライヤー様からPDFで見積書を受け取り、
それを自社で用意したExcelファイルなどに一件一件手入力する作業がありました。
設計変更が入れば見積内容も変わりますが、それらは個別フォルダや担当者別フォルダで保存され、
「最終的な量産契約見積書」だけが共通の場所に保管されるという流れでした。
このプロセスでは途中経過が可視化されず、過去の推移や前提条件の確認が困難なため、
調達担当者の工数やリスクが大きかったのです。
こうした現状を打破したく、UPCYCLEの導入に前向きになりました。
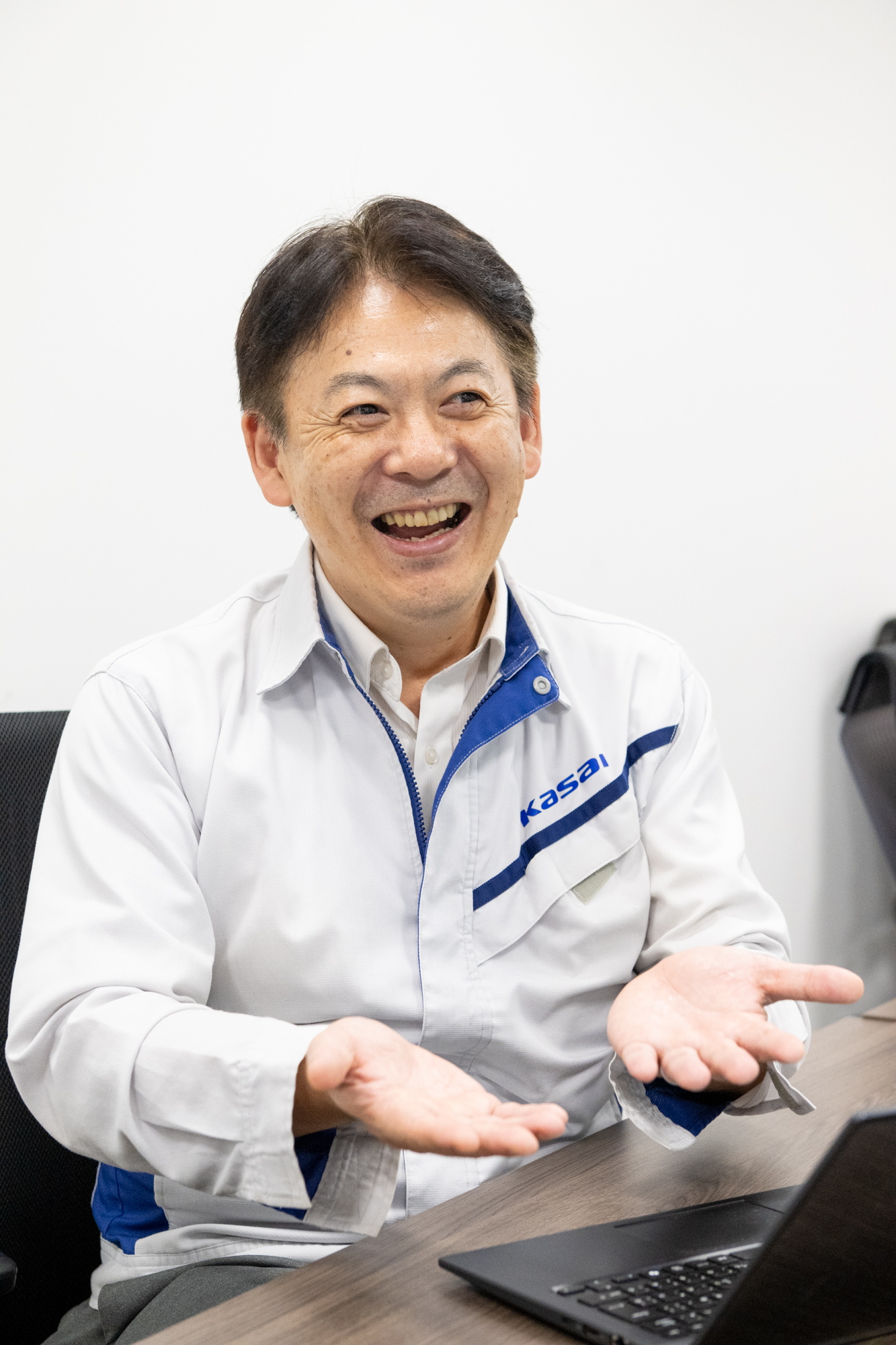
統一フォーマットで情報を網羅・活用することが、UPCYCLEの強み
下原 導入にあたって最も評価したのは、「PDFをそのままアップロードすれば、
UPCYCLEの中のフォーマットに整理される」という点です。
形式や書式が異なる見積でも問題なく、見積明細が統一されたデータとして取り込まれます。
これにより、過去案件との比較や、類似部品・材料間での差異要因の分析がしやすくなりました。
また、コスト比較も履歴を遡れることが大きい。
従来は「この案件はいくらだったか」「似た条件で他社がどの見積を出したか」といったデータを探すのに時間がかかっていましたが、
UPCYCLEであればそのような情報を引き出し、判断材料として使いやすくなります。
松原 多くの購買システムは、バイヤーが指定したフォーマットにシステム上から
サプライヤー様が見積回答を行う仕組みが大半です。
弊社が2018年の創業後にリリースした「RFQクラウド」というシステムも同様の仕組みでした。
一見良さそうに見えるこの仕組みですが、利用企業様で「見積がシステム上に集まりきらない」という問題にしばしば直面しました。
なぜなら、サプライヤー様はそれぞれ独自のフォーマットをお持ちであり、
バイヤー指定のフォーマットに見積入力することは「二度手間」になってしまうという難しさがあるからです。
また、「バイヤー指定のフォーマットではサプライヤー様の見積を表現しきれない」という問題も発生しました。
その結果、サプライヤー様独自のフォーマットで作成した見積を「添付する」形になり、
受領した見積書のデータを活用できないケースが大半でした。
UPCYCLEは、「サプライヤー様に行動変容を強制すること」の難しさを受け止めた上で、
「共通フォーマットにデータを転記する」プロセスをテクノロジーの力で解決することを前提としています。
AIを活用してバラバラな情報を一つのフォーマットに統一することにより、
網羅性を確保できることが最大の強みです。
下原 サプライヤー様の事情や、弊社のExcelフォーマットが製品の価格構造に合っていない場合には、
フォーマット通りにお見積書を入手できないケースもあります。
PDFの方が多い場合もありますし、部品と材料で提出スタイルが異なることもあります。
そういう中でもUPCYCLEがうまく機能していると感じています。
導入推進の実際と、現場での工夫
松原 UPCYCLEの導入にあたり、現場からは抵抗なく受け入れられたでしょうか?
下原 全社に広げる前に、一部メンバーでのトライアル期間を設けました。
さらに推進チームを組んで、“抵抗勢力”と感じられる人たちにも理解してもらうことに注力しました。
説明会も実施しましたが、全部を解説するのではなく、
使いながらオープンクエスチョンを投げる形式で行うことで、利便性を体感してもらうようにしました。
こうしたステップを踏んで浸透を図った結果、現在は全社運用が間もなく完了する段階です。
見積集約のその先に──自動車業界で「妥当な価格」をどうつくるか
松原 今後のUPCYCLEのアップデートとして、見積書記載情報だけでなく、
サプライヤー様との面談内容やコストダウンの企画や履歴などを蓄積し、
そこから“調達業務の様々なシーンでAIがレコメンド”を出すような仕組みを開発中です。
例えば、「表面処理はこの方式ではなく、あの方式の方がコスト・性能両面で良いのではないか」
といった提案が自動的に出てくるようなイメージです。
このような機能を提供できれば、これまで属人化されていた情報を組織知として活用できるようになり、
より効率的で高度な判断や意思決定を再現性高く行うことができると考えています。
下原 当社でも、現場で議事録や打ち合わせ内容をクラウドサービスにアップロードする体制を整えています。
これらの過去データが活用されてAIがインサイトを提供してくれるのであれば、
日常業務に対するサポートが一層充実すると思いますね。
松原 自動車業界における“妥当な価格”とは何かを考えた時、
多くのバイヤーが納得感を持つのは「熟練したバイヤーが査定した結果に辿り着くコスト」だと思います。
言い換えると、見積金額の検討プロセスが妥当か──
過去の情報が蓄積され、比較や検討がきちんと行われているか──という点が大きい。
そうしたプロセスをデータとテクノロジーでサポートすることが、
UPCYCLEの使命だと考えています。
下原 今後もさらなるアップデートを期待しています。
弊社でも調達部門だけでなく、設計部門や原価企画部門との連携拡大も検討中です。