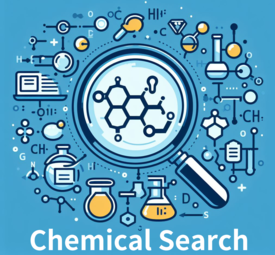用途や今後の市場動向について解説
「ウレタンシール材/ウレタンシーリング材」は、主に土木建築の現場で幅広く利用されています。
世界を見渡すと、地域によってはシリコーン系のシール材などが台頭している側面もありますが、東南アジア等ではウレタン系シール材の需要はむしろ増加しており、しばらくウレタンシール材が市場から消える様子はありません。
ウレタンリース材は非常にすぐれた特性を持っており、さまざまな場面で利用可能です。本記事ではウレタンシール材の用途や、市場・価格動向などについて解説します。
そもそもウレタンシール材とは
ウレタンシール材とは、「ポリウレタンを主成分として使われたシール材」のことを指します。
ちなみにポリウレタンとは、ウレタン結合基を含んだポリマーのこと。
ウレタンシール材は、非常に丈夫で使いやすいのが特徴です。
硬化すると弾力を持つという特性が、さまざまな場面において活用されています。
また、その他シール材と比較して高い密着性を有しているというのも、幅広く使われている要因のひとつです。


ウレタンシール材の材料は何か?
ウレタンシール材の材料は、おおむね以下のようになっています。
| ポリオール・イソシアネート | 30~70% |
| 溶媒 | 10~20% |
| 添加剤(安定剤・触媒ほか) | 5~30% |
一般にポリオールとイソシアネートの樹脂成分は30%から50%と、全体の半分以下におさえられます。
ただし、シンナーやトルエンなどのいわゆる「VOC」対応を行っているグレードに関しては、樹脂成分成分の比率は50%から70%程度と高めに調整されます。
ウレタンシール材の種類
ウレタンシール材には、ふたつの種類が存在します。
同じウレタンシール材でも特性はまったく異なっている点には、注意が必要です。
1成分形
「1成分形」とは、「湿気を浴びて硬くなる」という性質を持つものです。
この性質は、一般的に「湿気硬化性」と呼ばれています。
特別な手間はかからず、カートリッジを開けてすぐに使用できる、とても便利なシール材。
一方で2成分形と比較して、コストが高いのが欠点となっています。
2成分形
もうひとつは、「2成分形」と呼ばれるものです。
2成分形のウレタンシール素材は、「ポリオールとイソシアネートが結びつき合うことで硬くなるという性質を持っています。
いわゆる、「反応硬化性」と呼ばれるものです。
1成分形と違って、撹拌機で攪拌(かくはん)してからでないと使えないという特性を持っており、使用には若干の手間が発生します。
ただし1成分形と比較して材料費がかからず低コストなのが特徴で、大量にウレタンシール材が必要となる大型の建築物などで積極的に用いられます。
主剤・硬化剤について
主剤と硬化剤については、主に以下のように組み合わせられます。
- (主)PPG×(硬)MIDI
- (主)PPG×(硬)TDI
PPGを主剤とすることで、耐熱性や弾性を、ある程度コントロールすることが可能です。
硬化剤としてHDI、IPDIといった特殊イソシアネートを使うことも可能ですが、使用される用途はかなり限定的です。
なぜなら、現状ではMDI・TDIを使った場合と比べて、すぐれたメリットが見出されていないからです。
HDI・IPDIを使った場合、「黄変しづらい」というメリットが得られますが、一方で「反応性が悪い」・「コストがかかる」というデメリットも生じます。
そして「黄変しづらい」ということは、反応性とコストよりも重視されるケースがほとんどありません。
現時点での主なウレタンシール材メーカーとしては、以下のような企業が挙げられます。
ウレタンシール材市場規模推
2017年から2020年までの間で若干の縮小があり、今後もわずかながら減衰していくと予測されています。
販売数量が減衰する背景としては、
- 建築物の着工件数減少
- ウレタンシール材からシリコーン系シール材へのシフト
などが考えられます。
今後もウレタンシール材が大幅に需要を伸ばす見込みはなく、少しずつ市場は縮小していくでしょう。
ただ、世界全体の市場においてはその限りではありません。
まず2017年から2019年にかけては、一貫して販売数量が増加し、2020年以降も増加が予測されています。
というように国内市場の縮小するに反して、世界での市場規模は拡大へ向かっているというわけです。
中国では、欧米及び中国現地メーカーのウレタンシール材が、広く流通しています。
年間をとおして寒暖差が大きい地方では、ウレタンシール材の耐久性が高く評価されているため、ニーズを広げ続けているというわけです。
東南アジアなどの発展途上国においては、建築需要が拡大しています。
よって相対的に低価格なウレタンシール材に対する需要拡大があり、販売数量も増加しているというわけです。
一方で欧米諸国などの先進国では「イソシアネートには有害性があり、濫用すべきでない」という思想が広まっています。
よって欧米諸国では、ウレタンシール材よりもシリコーン系シール材へとシフトする流れが認められます。
ウレタンシール材を使うメリット・デメリット
というようにウレタンシール材は、現在でも幅広く使われている、たいへん有用性の高い存在です。
実際にウレタンシール材を使うことで得られる、メリットとデメリットについて解説します。
ウレタンシール材のメリット
ウレタンシール材のメリットは、長きに渡って広く利用されていることからもわかるように、さまざま存在します。
特に以下のような点は、ウレタンシール材におけるもっとも強力なメリットであると言えるでしょう。
耐久性が非常に高い
まず、耐久性にすぐれるという点が挙げられるでしょう。
物理的な衝撃に対して堅牢であり、安心して利用できます。
密着性が高い
ウレタンシール材が持つ密着性は、多くの目地への利用につながっています。
密着することで隙間を埋められるため、外壁や軽微な陥没などにおいては特に有効です。
上から塗料を重ねられる
ウレタンシール材は、上から塗料をかさねることが可能です。
というよりも後述する紫外線に対する脆弱性から、むしろ塗料を重ねることが推奨されます。
比較的コストが低い
幅広く使われる理由のひとつとして、「比較的コストが低い」という点が挙げられます。
競合となるシリコンなどと比較すれば、コストは大きくおさえられることが可能です。
以下は、ウレタン・シリコンのシーリング材を、用途上において重要な観点で比較した表です。
| 比較点 | ウレタンシール材 | シリコンシール材 |
| コスト | ○ | × |
| 耐久性 | ○ | × |
| 耐熱性 | × | ○ |
| 耐候性 | × | ○ |
| 乾燥性 | × | ○ |
というようにコストと耐久性の面では、ウレタンシール材は、シリコンのそれを上回ります。
そして、コストが低いうえに耐久性でも上回っているというのは、ウレタンシール材の大きな強みとも言えるでしょう。
「安くて丈夫」という分かりやすいメリットがあるため、幅広く使われているわけです。
ただしシリコンシール材とは相互補完の関係にあり、耐熱・耐候・乾燥性といった面では劣ります。
したがって状況や用途によって、適切なものを使い分けることが重要です。
ウレタンシール材のデメリット
というようにウレタンシール材は、さまざまなメリットを持ち合わせています。
いっぽうで、以下のようなデメリットが存在することも、理解しておかなければいけません。
メリットとデメリットを比較したうえで、ウレタンシール材の導入について考えるのが重要です。
紫外線に弱く、対策を要する
デメリットとしては、まず「紫外線に弱い」という点が挙げられます。
したがって目地が外装部分である場合、紫外線による劣化は避けられません。
劣化対策として、耐候塗料を重ねるなどして、ウレタンシール材へ紫外線が直射しないようにするといった対応が必要になります。
ブリードしやすい
物理的な耐久性が高い反面ブリード(汚染)に弱いという欠点も抱えています。
ウレタンシール材は、そもそも「ほこりなどを引き寄せる」という性質を持ったものです。
これによりウレタンシール材の目地は、ブリードされやすくなります。
ウレタンシール材を使う場合は、定期的なメンテナンスでブリードを除去する必要があるでしょう。
どんなときにウレタンシール材が使われるか?
ウレタンシール材は、その汎用性の高さから、さまざまな場面で用いられます。
- 建築物の内装・外装
- サッシ
- 自動車
- ALC目地
- 窯業系サイディング
- コンクリートの補修etc…
というように、幅広い場面において、ウレタンシール材は効果を発揮しています。
まとめ
ウレタンシール材は、低コストでありながら、きわめて高い有用性を有しています。
特に建築土木分野では、法人・個人を問わず、幅広く利用する機会があるでしょう。
市場動向については、現在日本ではわずかな縮小傾向が認められます。
ウレタンシール材の代替えとなる塗料はまだ成長途上にあり、すぐさま市場から排斥されるとは考えづらいでしょう。
世界的に見れば、明らかな市場拡大傾向が認められます。
特に中国や東南アジアなど建築需要が肥大化している部分では、ウレタンシール材は強く求められています。